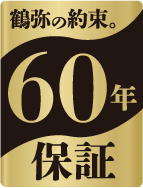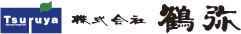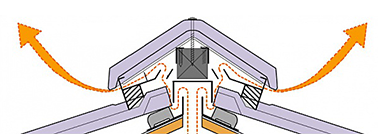スタッフブログ
カレンダー
最近のエントリー
2026/01/19
北陸支店 出荷担当者の1日をご紹介します
2026/01/13
魅せる瓦
2026/01/06
仕事始め式を開催しました
2026/01/06
ブログ大賞
2025/12/22
先日外部セミナーで・・・
2025/12/15
なが~く楽しめる趣味
2025/12/08
製品横持ちのお仕事
2025/12/01
給湯器盗難
2025/11/25
AIとはどんなもの?
2025/11/17
明るい色の屋根はどうですか?
2025/09
02(火)
こんにちは。鶴弥 新入社員の平山です。
私は瓦が好きで鶴弥に入社したのですが
大学の卒業論文でも瓦について研究していたので一部ご紹介したいと思います!
そもそも瓦は寺社仏閣や城郭など重要な建物で用いられ
江戸時代になると町屋などの民家にも使われるようになります。
それに伴い様々な地域で特有の瓦を生産するようになっていき
近江国八幡多賀村(現滋賀県近江八幡市)では
『八幡瓦』といういぶし瓦が作られていました。
江戸時代中期には瓦生産者の増加によって
作った瓦に生産者の名前、生産日、生産場所などを彫るようになり
八幡瓦でも近江八幡市若宮町の教信寺にある
元禄11年(1698)に作られた『八幡瓦師 寺本仁兵衛』の銘がある鬼瓦が
最古の八幡瓦として確認されています。
寺本仁兵衛のほかにもたくさんの瓦師が瓦に名を残しており
大きな鬼瓦の鰭部分に残されている場合が多いです。
調査を進めると、垣内平兵衛や前田平四郎、和田吉兵衛、福井増右衛門、奥田七郎兵衛
など多くの瓦師がいたことが明らかになりました。
また、18世紀末頃になると瓦師たちは勢力を強め、瓦工房を経営しながら
鬼師と呼ばれる鬼瓦や飾り瓦などの立体的な瓦をつくる専門の職人を雇うように
なっていき、『細工人 坪井三五郎 春忠』と記された
2人の鬼師が共同で作ったと考えられる鬼瓦も発見されました。
このような瓦銘は滋賀県だけでなく全国どこにでも見られ、三州瓦にも残されています。
高浜市の春日神社に奉納されていた瓦焼狛犬には
「享保八年 三州高浜村瓦屋甚六 瓦師四郎兵衛 同師七左エ門 作」
という文字が彫られており
享保8年(1723)には確実に瓦師が高浜に存在したことがわかります。
また、三州瓦職人は美濃、信州、北関東、
さらに東北地方までにも勢力を伸ばしていたため
どこか遠い地に三州の名前が入っている瓦が今でも残っているかもしれませんね。

立派な瓦を保存している寺院は多いため、
皆さんも大きな瓦を見つけたときは文字がないか
探してみるのはどうでしょうか。
もしかしたら古い瓦を見つけられるかも…?